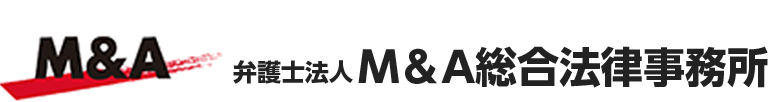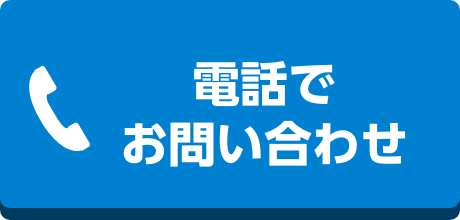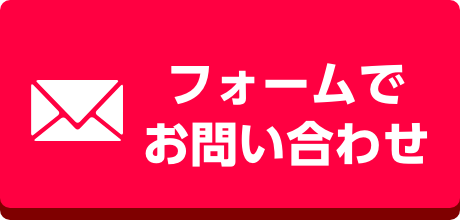京都新聞元相談役への役員報酬返還訴訟事件、何が問題なのか?

関西の名門地方紙と言われている京都新聞で、大株主でオーナー家である白石家と現経営陣との間の訴訟問題が起こり、現在も争いが継続しています。
訴訟では、京都新聞ホールディングスと子会社2社から違法な利益供与が行われていたとして、京都新聞の現経営陣が白石浩子氏に対して5億1096万円の返還を求めています。そして、今年1月23日に第1審である京都地裁は、白石浩子氏に対して受け取った報酬の全額返還を命じる判決を出しました。
また、一方で、昨年末にかけて、白石浩子氏は保有する京都新聞ホールディングス社の株式を東京のファンド関連会社に売却し、その後、京都新聞ホールディングス側はその株式を買い戻したようです。
現在までの京都新聞の現経営陣とオーナー家との係争の概要はこのような状況ですが、京都新聞ホールディングスの現経営陣はなぜ創業家の白石浩子氏に対して訴訟を提起したのか、そして、その対応のために創業家の白石浩子氏はどのような対応をし、そもそも、このように両者間の争いが大きくなった背景には、どのような本質的な問題点があると考えられるのか?などについて検証、説明したいと思います。
京都新聞の成り立ち
京都新聞は、京都府および滋賀県を中心に発行されている地方新聞で、創刊140年あまりの歴史を持つオーナー家が大きな力を持つ新聞社です。このようにオーナー家が大きな力を持つ新聞社は、地方紙を中心に存在し、その数は決して少なくはありません。
京都新聞の起源は明治12年(1879年)、京都の経済情報を迅速に伝えることを目的として創刊した「京都商事迅報」にまで遡ります。
その後、名称変更を重ね、第二次世界大戦中の1942年に「京都商事迅報」の流れを汲む「京都日日新聞」と「京都日出新聞」とが合併し「京都新聞」が誕生しました。
そして、近年になって、社会全体の経営環境が変わる中で、京都新聞は、2006年(平成18年)にはグループ経営に移行し、編集・制作を行う「株式会社京都新聞社」、広告営業・新聞販売を担当する「株式会社京都新聞COM」、新聞印刷を手掛ける「株式会社京都新聞印刷」の3社に分社化しました。
さらに、2014年(平成26年)には持株会社体制に移行し、商号を「株式会社京都新聞ホールディングス」に変更しています。
役員報酬返還訴訟に至る経緯
京都新聞ホールディングスの現経営陣がオーナー家の一員である白石浩子氏に役員報酬の返還訴訟をすることになった要因について、京都新聞ホールディングスの現経営陣は、オーナー家の白石浩子氏と以前に京都新聞社社長であった坂上守男氏との間で違法な利益供与とみられるような取引があったと主張しています。
京都新聞ホールディングスの経営陣曰く、その内容は、昭和60年(1985年)6月3日付けの「確約書」に書かれており、この「確約書」の末尾には、「白石浩子」と「坂上守男」、そして双方の立会人である弁護士の署名捺印がされています。
「坂上守男」氏は当時の京都新聞社の社長で、この「確約書」によって代表取締役社長としての地位を保証された坂上氏は、その後10年にわたって京都新聞社の社長として在任し、1995年からは会長も兼務、2003年に相談役に退くまで20年にわたって京都新聞の代表権を持つ地位に就いていました。
現経営陣は、この「確約書」に基づいて京都新聞社側は白石浩子氏に長年にわたって違法な利益供与が続けられ、その金額は約19億円にも上ると主張しており、そのうち時効にかかっていないものなどの合計5億1,096万円の返還を求めています。
元相談役とはどのような人物なのか
白石浩子氏は、代々の京都新聞のオーナー家の子孫である白石英司氏と婚姻関係にありました。白石浩子氏は、白石英司氏が1983年に急逝した後、1983年からは京都新聞とKBS京都の会長職に就き、1987年から2021年までの37年間、京都新聞および京都新聞ホールディングスの相談役を務めました。
また、白石浩子氏が京都新聞社とKBS京都の会長職に就いた直後、KBS京都と京都新聞社に約98億円の簿外債務が発覚し、簿外債務の処理をめぐり内紛が勃発した際には、数人のフィクサーを挟んで京都新聞社とKBS京都の経営をそれぞれ独立させるということで決着をつけました。
このようなやり取りをする中で、既に説明したとおり、当時の京都新聞の社長であった坂上守男氏と利益供与についての合意をしたとされています。
そして、今回、この京都新聞から白石浩子氏への利益供与について、京都新聞の現経営陣から違法であると提訴され、今年に入って第1審の京都地裁が、役員報酬等の返還を命じる判決を出したということです。
一方で、白石浩子氏は自らが持っていた京都新聞ホールディングスの株式計341万株(発行済み株式の28.4%)を2024年10月末に東京の投資ファンドに譲渡しました。なお、この際、京都新聞ホールディングス側はこの譲渡を承認しています。
その後、京都新聞ホールディングスは、2024年12月26日の臨時株主総会で、その株式すべてを約20億円でそのファンドから株式を買い戻すことを決議しました。これにより、京都新聞は白石浩子氏との資本関係を完全に解消することになりました。
役員報酬訴訟の争点は何か?
京都新聞ホールディングスの現経営陣は、2022年6月22日に白石浩子氏に対して、5億1,096万円の報酬返還を求めて京都地裁に提訴をしました。
京都新聞ホールディングス側は、白石浩子氏に対して長年に亘って、ほとんど実質的な業務を行っていないにもかかわらず、京都新聞ホールディングス側から多額の報酬や私邸の管理費用が支払われていたことが、会社法に違反する利益供与に該当すると主張しています。
一方で、白石浩子氏側は、相談役の報酬は名誉職の社主や社友と同じ慣行で支給されたもので、利益供与にあたらず、違法な利益供与であったとは立証されていないなどとして請求棄却を求めています。
この役員報酬訴訟の主な争点は、白石氏が相談役としての報酬に見合う業務を実際に行っていたかどうか、そしてその報酬や私邸の管理費用の会社負担が、会社法で禁じられている特定株主への利益供与に該当するかどうか、という点です。
この争点を判断するうえで、非常に重要な意味を持つのが、前述した昭和60年(1985年)6月3日付けで京都新聞社社長であった坂上守男氏と白石浩子氏との間で取り交わされた「確約書」とされています。
現経営陣は、この「確約書」によって、オーナー家の代表である白石浩子氏は、坂上守男氏の京都新聞社での社長などの地位を約束し、その経営について口出ししない代わりに、京都新聞側から多額の報酬を受け取るということを約束したと主張しています。
当初、白石浩子氏は、この「確約書」の存在を否定していましたが、京都新聞社内でこの「確約書」が発見され、報酬の意味合いについて、京都新聞ホールディングスの現経営陣が主張している内容が正しいとみられる重要な要素になったと考えられています。
しかし、この「確約書」の内容を見る限りにおいては、その項目に書かれている内容が京都新聞社から白石浩子氏に報酬を支払った根拠であると明確には読めないとも解釈できそうです。
二項目からなるこの「確約書」の内容は、
- 創業者である白石家を代表する白石浩子氏が節度あるオーナーとして努力する一方、当時の京都新聞社の社長である坂上守男氏が白石家を代表する白石浩子氏の地位、権限を支持し、尊重して京都新聞社の経営の充実と発展に寄与する
- 上記の確約に沿ってその職責を全うすることを前提に、白石浩子氏は坂上守男氏に対して社会通念上相当な期間、京都新聞社の社長としての地位を保証する
と書かれているように読めます。
よって、「確約書」は、それ以上の内容を定めたものでなく、この「確約書」をもって京都新聞社から白石浩子氏に支払われた報酬が違法であるとは言えないというのが、白石浩子氏側の主張だと考えられます。
また、そもそも、オーナー家の実務から退いている代表者などを社主、社友、相談役などの名誉職に就かせて、企業がオーナー家に対して報酬を支払うことは、他のオーナー企業でも行われている慣例であり、京都新聞社の場合も、この例から外れたものであるとまでは言えないということも、白石浩子氏側の主張だと考えられます。
京都地裁は、これらのお互いの主張を検討した結果、京都新聞ホールディングス側が証拠として提出した「確約書」による白石浩子氏と以前の社長であった坂上守男氏との合意の事実を認め、次のように判断しました。
- 本件確約書の第一項は、被告が、坂上が第二項の確約を守ることを前提にして、経営に口を出さないことと坂上の代表取締役社長としての地位を保証することが内容とされている
- 第二項の文言は、抽象的ではあるが、本件確約書の作成前、被告が坂上ら役員に対して大株主としての力を誇示したこと、本件確約書の作成後に、被告の求めに応じて巨額の報酬の支払いが開始されたことからすると、第二項の「乙自身はもとより新聞社及び関係企業グループの役員を指導して、新聞社定款に定める甲の地位、権限を支持、尊重して行動せしめ」との文言は、被告に対して巨額の相談役報酬を支払うことを意味していたと認められる
これらの理由により、京都地裁は、白石浩子氏に対して5億1,096万円の返還を命じる判決を言い渡しました。
訴訟に隠れている本質的な問題点
京都新聞ホールディングスの現経営陣によるオーナー家の代表に対する報酬返還訴訟では、その報酬の支給に違法性があるかどうかが争われており、前述のとおり、その主な争点は、報酬に見合った業務を実際に行っていたかということでした。
しかし、この京都新聞の一連の問題では、その訴訟での争点以外にも本質的な問題点があると考えられています。
その1つは、近年、企業のオーナー家に名誉職を与え、報酬を支払うという慣例が、徐々に見直される傾向にあるということです。上場企業などにおいては、相談役や顧問制度を廃止したり、社友や名誉職への報酬の支給を行わないと決めていたりする企業が増えています。
このような傾向からすれば、オーナー家に対する報酬は株主に対する配当など、できるだけ社内外から見ても透明性のあるものにするべきだという考え方が広まりつつあります。
また、会社の経営の代表者が、京都新聞での「確約書」で交わされた、オーナー家の意向に沿うことによって会社経営の代表者である地位の保証をうけるというような取り決めをすることは、企業の独立性やガバナンスの欠如が問われるということも起こり得ます。
特に、京都新聞は報道を行う立場であることから、一定の公平性が求められる企業であり、その企業がオーナー家の意向に沿った会社運営を行うことを約束している状態でその使命が果たせるのか?ということも今回の事件では問われ、特にマスコミなどはその報道で、オーナー家の影響力が増すようなこのような取り決めを認めることには否定的な立場を取る傾向が強くなっているように見受けられます。
他方、オーナーとしては、対象会社は上場会社でもないし、筆頭株主であるのだから、経営に関与したいという意向は強く存在し、それに対して、経営陣としては、自分たちだけで経営を行いたい、オーナー家を排除して支配権を維持したいとの意向も存在し、この綱引きの中で紛争が生ずることが多くなっており、本件もそのような株主間支配権争奪紛争の一種だと思われます。
オーナーとしても、会社から排除され、株式も塩漬けにされ、現金化もできず、配当金も十分もらえない、にもかかわらず、相続が生じた場合は、巨額の相続税だけを背負わされる状態であると思われ、引くに引けない非常にかわいそうな状態に陥り、本件の場合、その結果、敵対的な投資ファンドに株式を売却するということが生じたものと思われます。
今後の見通し
前述のとおり、2025年1月23日に第1審の京都地裁で、被告の白石浩子氏に対して5億1,096万円の全額返還命令の判決が出されました。白石浩子氏側は控訴する意向だと伝えられており、今後も裁判が継続する可能性があります。
原告の京都新聞ホールディングスの現経営陣は、第1審で示されたとおり、白石浩子氏と当時の京都新聞の社長であった坂上守男氏との「確約書」に基づいて支払われた報酬は違法であるという主張を続けることになると考えられます。
一方で、白石浩子氏側は「こちらから報酬を要求したり、圧力をかけたりしたことはない。法的に争っていきたい」と反論しており、「確約書」に書かれている内容も、それ自体では報酬を要求しているとまでは読めないことから、裁判が継続した場合には、結論が出るまでにさらに時間を要すると思われます。
京都新聞事件のまとめ
今回は、現在進行している京都新聞ホールディングスの現経営陣とオーナー家との訴訟の問題について、その背景やお互いの主張、今後の見通しなどについて検証してみました。
日本の企業、特に中小企業では、オーナー家と企業の経営者が同一であるということが多く見られます。一方で、企業の経営期間が長くなると、オーナー家以外の経営者に企業経営を任せるということが起こり得ますが、その際に、今回京都新聞で起こったようなオーナー家と経営陣との争いが起こる可能性があります。
特にオーナー家以外の経営者が続くと、オーナー家に対するロイヤリティが薄れ、オーナー家に対する処遇に対して疑問を持つ経営陣や社員が増えていく傾向がよく見られます。
一方で、上場企業ではない企業のオーナー家は、対象企業の株式の売却もままならず、充分な配当金も得られないというような状況が、中小企業の場合には多く見られます。
このような、企業のオーナー家として、あまりメリットが得られないような場合でも、例えば、代々オーナー家を引き継いでいくためには、多額の相続税が発生することとなります。
企業のオーナーかつ大株主して、その企業を継続していくために、それに見合う相応な処遇を求めたくなるという心情も理解できるところです。
このような事態に適切に対応することが、創業家や大株主として、オーナー家がその所有する企業に一定の影響力を持ち続けて経営を続けていくためには必要であるということが、この事例から理解することができると思います。